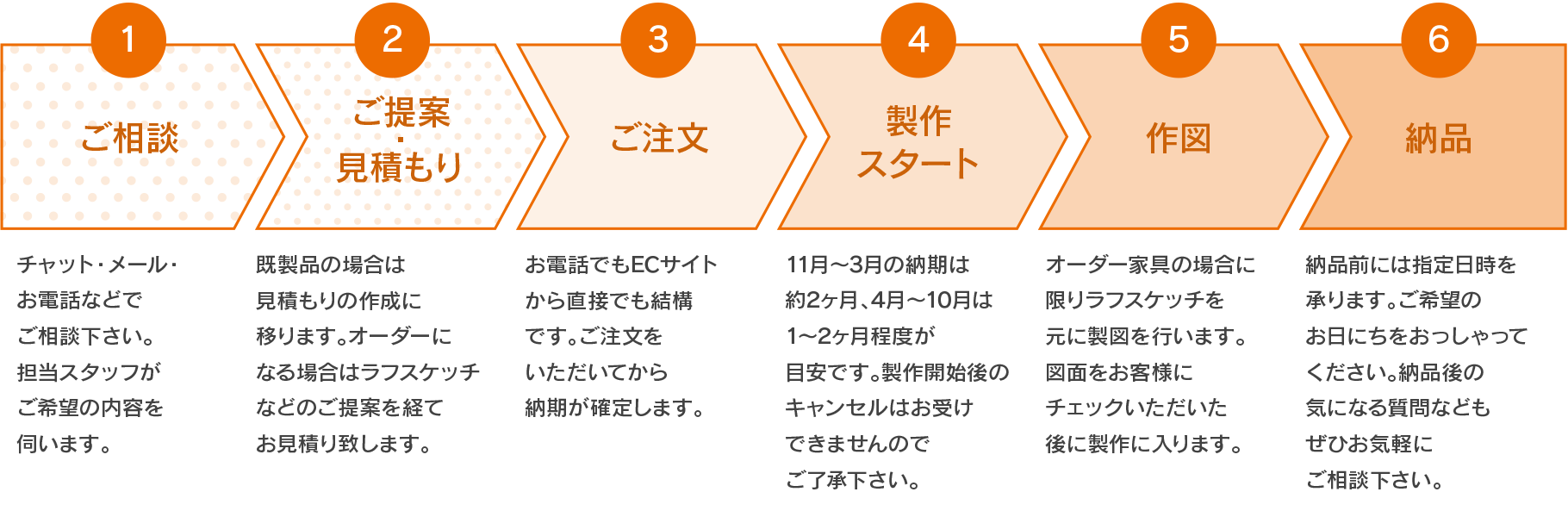子どもたちの「見えないけど見える」を形に
― 匠と保育現場が語る、オーダーメイド家具の魅力とこれから ―
今回は、保育施設向けのオーダーメイド家具を手がける「なかよしライブラリー」の職人さん、そして実際にその家具を日々使っている保育現場の利用者さんにインタビュー。使う人のリアルな声、作る人の細部へのこだわり、そして未来に向けた展望までをお届けします。
>さくらづか保育園はこちら


「子どものおもちゃが、棚につながったんです」
まず最初に、なかよしライブラリーの家具を導入されたきっかけを教えてください。
園長先生:
もともとは、自分の子どもにおもちゃを買ったのが最初の出会いだったんです。高知県のイベントで”なかよしライブラリー”を見つけて、「かわいいな」と思って。そこから「棚も作っている」と知って、調べて依頼したのが始まりでした。
なかよしライブラリースタッフ:
なるほど。おもちゃが入り口だったんですね。他にも、導入の決め手になったポイントはありますか?
園長先生:
いろいろあります。まず、木材のこだわり。それから、保育雑誌で見るような家具よりも価格が現実的で、園としても導入しやすかったです。そして何より、私たちの細かな要望にも柔軟に応えてくれる姿勢が決め手でしたね。

現場に寄り添うオーダーメイドの力
なかよしライブラリースタッフ:
最近の保育現場では、「コーナー遊び」など新しい保育スタイルが広がっていると聞きました。そういったニーズにも対応されているのでしょうか?
園長先生:
はい。コーナー遊びに合った棚や仕切りをお願いできるのは本当にありがたいです。「それぞれの保育室に合うように仕切りたい」という具体的な要望にも応えてもらえるので、他の園でも同じように相談する方が増えているみたいですよ。

子どもの“ちょうどいい”を形にする
――実際に使ってみて、使い心地はいかがですか?
園長先生:
とても良いです。特に、子どもが「見えるけど見えない」くらいの絶妙な高さを再現してくれるところがオーダーメイドならでは。見た目もすごくきれいで、全体的に「満足いってます」って感じです(笑)。
なかよしライブラリースタッフ:
ありがとうございます。例えば、背板をあえて無くしたり、扉を柵にして視線が通るようにする工夫もしています。ただ、完全に覆ってしまうと空間が狭く感じられるので、「閉じすぎず、抜け感を残す」ような設計にしています。
現場からのリアルな課題
――一方で、使っていく中で課題を感じる点もありますか?
園長先生:
棚で仕切ってしまうと、どうしても空間が詰まってしまうんです。パネル式の方が空間を活かせそうだけど、倒れるリスクもある。現状は柱で固定する“壁”のような仕切りを使っているんですが、それも棚が多すぎると空間に“抜け”がなくなるので…。
なかよしライブラリースタッフ:
そこは私たちも課題です。日々改善を行っていきます。

“ちょっとずつ”進化するものづくり
――そのような課題に対して、今後の改良予定はありますか?
なかよしライブラリースタッフ:
今後の改良予定もありまして。まずは扉ですね。新しい固定方法を試しています。
園長先生:
それは本当に期待しています。完成したら、ぜひ今の扉も買い替えたいです。
職人さん:
ありがとうございます。「ちょっとずつ解決していく」のが私たちのスタイルなんです。現場の声を大事にしながら、常にアップデートしていきたいと思っています。
おわりに ― 目に見えない“想い”を形にする仕事
今回のインタビューを通して見えてきたのは、「家具を作る」という行為を超えて、子どもの成長と保育の未来を支える空間づくりに真剣に向き合う人たちの姿でした。
保育現場の声に耳を傾け、その日常の中にある「ちょっとした困りごと」にも真摯に応える。そして、「子どもたちの目線」や「成長」に寄り添いながら、使いやすく、美しく、そして安心できる家具を生み出していく。
“見えないけど見える”
子どもたちが感じるその絶妙な感覚を、形にする匠の技が、今日もまた現場を支えています。